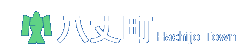神湊(かみなと)は三根(みつね)地域にある港。八丈島の難風である西南の風を遮(さえぎ)る所にあるので、かつては島随一(ずいいち)の商漁港とされていた。現在、底土(そこど)地区に商港として接岸港が完成し、神湊は漁港として利用されている。また大型客船が八丈島に寄港する際は、沖に停泊し、乗客が通船で上陸する港でもある。航海が非常に大きな危険の伴うものだった江戸時代の頃、島船が霧で遭難しかけ、神に祈ったところ、山上に女神が現れて船をこの港へ導いたことから、神湊という名がついた。
夕方帰り来る船の美しさが、八丈八景に謡(うた)われている。
追風に 神の港の 真帆(まほ)片(かた)帆(ほ)
夕日をきせて 帰る釣り舟
服部 弘道(はっとり こうどう)
服部弘道は樫立の人。博学で、弘化6年(1849年)に御船預り(おふねあずかり)役に就任し、維新後の明治5年(1872年)に八丈島で学制が布かれた際には、八丈島内の学区取締を務めた。
※御船預り役とは、幕府の官船の管理責任者で、航海時には船上で陣頭指揮を執った。八丈島では大変重要な地位だった。
※学区取締とは、学校教育を担当する役人のこと。